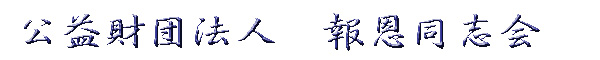 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報恩同志会は 公益財団法人報恩同志会は、純然たる修養団体であり、如何なる政治的、思想的、宗教的な団体にも属していません。 私たちの会は、多くの人々が元気で働き、明るく暮らし、和やかに話し合って、明るい家庭を築くべく努力し合う為の修養団体です。 聴講は無料です。 お話をまず聞いてみませんか! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「修養」は…健全なる精神が健康な肉体をつくる
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちの目指す日本人としてあるべき姿
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報恩同志会の歴史
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創始者等について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
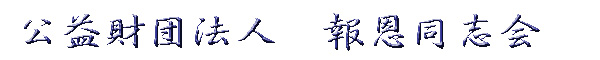 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報恩同志会は 公益財団法人報恩同志会は、純然たる修養団体であり、如何なる政治的、思想的、宗教的な団体にも属していません。 私たちの会は、多くの人々が元気で働き、明るく暮らし、和やかに話し合って、明るい家庭を築くべく努力し合う為の修養団体です。 聴講は無料です。 お話をまず聞いてみませんか! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「修養」は…健全なる精神が健康な肉体をつくる
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちの目指す日本人としてあるべき姿
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報恩同志会の歴史
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創始者等について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||
| 公益財団法人 報恩同志会 〒411-0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩1007-1 TEL:055-986-1222 |
||
| © Copyright 報恩同志会 2025. All Rights Reserved |